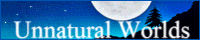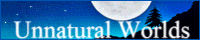Unnatural Worlds
雷鳴の領主
021
020 TOP 022
土の壁の中は真っ暗である。
「お前の補助魔法は凶悪だな」
パークスは、そう言わざるを得なかった。ジェンの補助魔法は、使った人間の魔法を数倍にするなど朝飯前ではある。しかし、単独では、優秀とはとても言えない魔法使い二人で、軍人から身を守り、土部屋の中で寛いでいる自分たちに、ある種の凶悪性がないとは言えない。そして、そうできるのは、ジェンのおかげである。
「強力であると言われたことはありますが、凶悪は初めてです」
目を丸くしていることが容易に想像できるジェンの声からは、彼が全く気付いていないことが分かる。
「お前の凶悪な補助魔法のおかげで、命の危険はないが、本当にどうする?」
確認も兼ねてそう尋ねてみると、はり的外れな答えが返ってくる。
「でも、やはりあなたの防御魔法は素晴らしいですね」
顔は勿論見えないが、ふわりと笑うジェンの笑顔は容易に想像ができる。
「僕以外に、防御魔法使う奴はいたか?」
パークスはそう尋ねた。
パークスは、自分の魔法については。多少どころではないコンプレックスを持つ。褒められてうれしいのだが、ついつい疑っているようなことを言ってしまう。
「地味ですから」
悪気のかけらもないジェンの言葉に、パークスは項垂れた。勿論、ジェンは視覚的にそれを確認することができないため、まさかパークスが自分の言葉で沈黙しているなどとは思いもしない。
土使いで、防御魔法を得意とする。それが、威力の高い雷使いのライアル、万能な闇使いのアン、広範囲に及ぶ水使いのリリーのいる魔法学校特別塔で、どれだけ地味なことか。魔法が地味でも、パークスが地味でなければ、まだ良かった。しかし、困ったことにパークスも十分地味である。
「そういえば、土魔法は、土が無くては使うことができませんから、あまり見る機会もありませんね」
それだけでは飽き足らず、ジェンは、追い打ちをかける。勿論、自覚はしていない。しかし、彼の言っていることは正しい。空気中の水分を使う水魔法や、空気中の塵や埃による静電気を使うことができる雷魔法と違い、土魔法は、使える場所が限定されている。それを発見したのが、魔法原理学のアズサ博士。妖界王太子騎士、つまりアンの騎士である。
弄られる苦労人で、現実逃避の名手であったのだが、一応魔法原理学の創始者であり、彼女を知らない人々からは、王太子に相応しい天才と言われた学者によって、地味であり、一般的ではないことが証明された土系統の魔法。
ジェンが自分の失態に気付くまで、それ程時間はかからない。
「すみません……代わりと言ってはなんですが、今回の功績を入れて成績をつけさせて頂きますね」
成績が良ければ嬉しいが、成績が何の意味もなさない魔法学校特別塔の生徒。毎度のことながら、一々落ち込んでいるパークスの心に、その言葉が響くはずがない。それ以前に、自分の失態を、成績で覆い隠すのは、教師としてどうだろう、と思っているパークスは、優秀な生徒だと言えるので、そちらを褒めるべきである。
暇で暇でしょうがなかったリリーとハヤは、森の中を走っていた。とりあえず、彼らが走っている一番の理由には、これが挙がる。
「遠足みたいだな」
勿論、遠足なんて言う生易しい速度で走っているわけではない。大体、遠足では普通、走らないものである。
天界人のいうのは、それ程身体能力は高くは無いのだがリリーは特別教室の中でも、かなり高い方だった。ハヤはエルフのため、森の中の移動は早い。二人は、ジェンとパークスの倍以上の速さで走っていた。
因みに、ライアルとアンは、リリーとハヤよりも森の中を速く移動できる。浮遊ができるアン、並はずれた跳躍力を持つライアルは、比較の対象にもならない速さで移動する。
「でも、大変なんでしょ」
リリーがそう尋ねると、ハヤは溜息を吐く。
「まぁ、大変ではあるが」
しかし、ハヤにどうにかできる次元の問題ではない。
火の国に怯えて、攻め込んでくる気配のない氷の国の軍。全く入ってこないライアルからの情報。何かがあったということをハヤは悟っていた。火の国を動かさないのは、ライアルの意志。雷の国の領主は、火の国の領主の傀儡では無い。
助けて貰うと、見返りが必要になってくる。しかし、助けなしでどうにかできるような問題でもない場合、牽制だけして貰うことがある。火の国と雷の国の間は、領主の許可があれば、自由に瞬間移動ができるため、呼び出すだけでも、それ程困ることはない。
とりあえず、様子を見に行こう、とハヤは思って、走っていた。しかし、それも長くは続かない。
「待て、この先に、誰かいる」
ハヤは片手でリリーの動きを制し、耳を済ませる。何よ、とでも言うかのように、リリーはハヤを見る。
「魔法が使われている音だ。それも、これは大人数だな」
無数の魔法の音と、そけを跳ね返しているかのような鈍い音。
ハヤは、背中にひやりとした汗が流れるのを感じた。ハヤとリリーの二人は、ジェンとパークスよりも足は速い。しかし、魔法戦に強い方ではない。ハヤは、リリーか魔法が決して得意ではないことを知っていた。魔法学校の生徒であるリリーは、魔法は苦手だときっぱりと言い切っていた。
「何か既視感のある魔法なんだけど……」
ハヤは、リリーの言葉に、素直に驚く。魔法学校特別塔の生徒がこの森にいるのである。
「魔法学校特別塔の生徒か?」
ハヤは、いつもの飄々とした声ではなく、真剣な声で尋ねる。ライアルを除外するのは、彼は魔法合戦などという面倒なことはしないからである。
「そうだと思うんだけど、誰だったかしら……土使いで……」
リリーは首を捻る。土魔法を使うパークス。その存在は思い出されない。
「人数が多くは無いだろう。誰だ? 影が薄いのか?」
ハヤは急かすように尋ねる。すると、リリーがぽん、と手を叩く。
「影が薄い……パークスだわ。妖界人。地味な土使い」
リリーの思い出す切欠となったのは、"影が薄い"という言葉だった。
020 TOP 022
Copyright(c) 2010 UNNATURAL WORLDS all rights reserved.