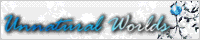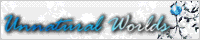Unnatural Worlds
勇気の色
029
028 TOP 030
特別塔生徒は、慰霊祭関係の仕事を頼まれる。シートを敷いたり、椅子を並べ替えたりする作業は、体力が必要だ。特別塔の生徒は、体力が有り余っており、なおかつ慰霊祭に出席しないため、格好の働き手なのだ。
しかし、それに呼ばれない者もいる。
とりあえず、ライアルが呼ばれることはない。アンとリリーも呼ばれない。問題児は呼ばれない。つまり、ライアルは勝手に行動していても良いのだ。妖界城から魔法学校に帰った翌日、ライアルは雷の国に戻った。戻るとすぐにハヤを呼び寄せる。
「お前、サクの友達だっただろう。十七歳までに、サクが雷の国から消えた時期はあったか?」
茶も出さず、椅子も勧めずに尋ねる。しかし、ハヤは勝手に椅子に座り、勝手にポットの中のお茶をマグカップに注ぎながら、あからさまに溜息を吐いた。
「サクかぁ……そういえば、奴は一時期消えた。ああ、あの荒らしまわった事件よりも前だったな」
サクが荒らしまわった事件は、エルフにとって重要なものだった。
「サクが何歳のときか覚えているか?」
覚えていなかったらただじゃ済まさないぞ、この役立たずが、という正直な気持ちを込めて、ライアルはハヤを睨みつけた。
「十四歳でいなくなって、戻ってきたのは十五歳の誕生日の半年後ぐらいだったかな?」
サクが戻ってきた時期、つまり、サクの十五歳の誕生日から半年後に、魔法学校虐殺事件が起きていた。
サクは、あの事件が起こったから、雷の国に戻ってきたのだろうか、とライアルが考えていると、ふと思い出したかのように、ハヤが言った。
「シヴァの方が知っているかもな」
あいつ、サクと仲良かったから、とにやりと笑うハヤに、シヴァを呼び出すように命じる。はいはい、と言いながら、身軽な体で飛び出していくハヤの背中を見ながら、ライアルは椅子にゆっくりと腰掛けた。
ライアルはサクの顔を知らない。サクが何であったかと言うことも知らない。知っていることはごく僅かなのだ。
「アンに直接聞ければいいんだけど……」
絶対教えてくれないだろうな、と思い、ライアルは溜息を吐いた。アンは、過去のことは一切喋らない。ライアルもそれを強要しないことにしていた。それが、悠久の時を生きるアンに対してできる、唯一の気遣いだと思っていたのだ。
呼び出されたシヴァは、ライアルを見るなり、溜息を吐いた。久しぶりに会った人に顔を見るなり溜息を吐かれるということは、ライアルにとっても我慢し難いことだった。
「何故、溜息を吐く」
シヴァは、別に、と素っ気ない返事をする。シヴァはいきなり呼び出されて不機嫌なんだろう、と思ったライアルは、深くは追求せずに尋ねる。
「単刀直入に尋ねるが、サクは妖界王太子に会っていたと言っていたか?」
「魔法学校については分からないが、あいつは、妖界王太子と会っていたと思う」
何故、そんなことを突然尋ねる、とでもいうような顔で、シヴァはそう答えた。
「結婚を渋るあいつが、母親に何と言ったと思う? 妖界王太子殿下なら、結婚しても良い、なんて言ったんだ。妖界王騎士は滅びれば良い、とも言っていたから、会っていたことは確実だろう」
サクが生きた時代、セイハイ族は権勢を振るっていたが、妖界王太子は用意できなかったらしい。
「妖界王太子騎士って、かの有名な東の冷たき魔法使いだよな」
アンには騎士がいて、その騎士を召喚できる。東の冷たき魔法使いというのは、魔法原理学の創始者である学者だ。アンは学者を騎士にしているのである。
「召喚して欲しいと言ったんだが……」
学者を騎士にする者も珍しいが、騎士になる学者も珍しい。ライアルはアンが騎士に選んだ学者に興味があったのだが、アンはライアルが頼んでも騎士を召喚してくれない。
「まぁ、殿下にも理由があるのだろう」
シヴァに諌めるように言われ、ライアルはそういう意図はなかったため不満に思った。しかし、彼是言うことはなかった。
「呼び出して悪かったな、シヴァ」
魔法学校に戻る前に礼を言う。
「シヴァだけかよ。俺は?」
すかさず訊いてくるハヤには、にやりと笑ってこう答える。
「ハヤは、次もちゃんと来いよ」
生意気領主、暴君、など言い放題のハヤと、溜息を吐くシヴァを置いて、ライアルは魔法学校に戻った。
残された二人は、ライアルの家で勝手にお茶を飲んでいた。ライアルの家には重要な物はないため、鍵がないのだ。それでも、他人の家なのだから、少しぐらいは遠慮するべきなのだが、二人は自分たちの家のように寛いでいた。
「サクの好みって分からないよな」
二人は今でも覚えている。雷の国を派手に荒らしまわっていった男女は、小さな子どもを抱えて戻ってきた。顔だけ見せて、さっさと帰ってしまったのだが、エルフにとっては衝撃的だった。
「元々、理解の範疇を超えた男だった」
最初に好意を示したのは、四界に名を轟かせる美女王太子だった。しかし、結局彼が選んだのは、美人と言えなくもないが、平凡と言った方がしっくりとくる女性だった。
それまで、サクは面食いだと思っていたエルフの一同は、皆驚いたのである。しかし、そのときのサクの年齢が、二十に満たなかったというのも勿論ある。
「それで、溜息の理由は?」
「父親に似るって残念なことだなぁ、と思って」
シヴァは、心底残念そうな表情で言った。ハヤは声を出して笑う。
「母親に似ていたらまだ良かったよな」
サク・セイハイ。セイハイ最後の当主になるはずだった男は、ライアルの父親だった。そして、その顔立ちは、ライアルにそっくりだった。その事実をライアルは知らないし、まさかそのせいで、自分が東の冷たき魔法使いに会わせて貰えないなどということは、夢にも思っていない。
「しかし、四楼様は美しいよな。両親に全然似ていない」
「似ていないから、四楼になれたんだろう。ほら、小さい頃から全然似ていなかった」
確かに、と笑い合う二人は、幼い頃のキナを知っているが、ライアルのことは知らない。
028 TOP 030
Copyright(c) 2010 UNNATURAL WORLDS all rights reserved.