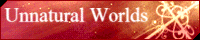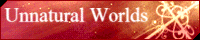Unnatural Worlds
勇気の色
030
029 TOP 031
ジェンとパークスは、慰霊祭の準備をしていた。二人は、黒い布を取りに行くために倉庫に向かっていた。
倉庫と会場は離れており、緑の茂る林を抜けなくてはいけない。緑の中には当然、動物がいる。そして、石垣が近くにあるような林に多いのは蛇である。つまり、小さな蛇に遭遇してしまうことは珍しくない。
ジェンは、小さな蛇を見つけるなり、鋭い息だけの小さな悲鳴をあげて、立ち止まって目を逸らす。パークスは、ジェンの突然の行動に驚きながら、小さな蛇を確認する。ジェンは、一瞬足を止めただけで、またすぐに歩き始める。
「ジェン、お前は蛇が苦手だったな」
ジェンは、逃げるように速足で歩いている。そんなジェンにパークスはそう言った。
「蛇というか、爬虫類の目が苦手なんです」
ジェンは困ってしまいます、とでもいうように肩をすくめる。そんなジェンに、気持ち悪いじゃなくて特定の部位が苦手というのは珍しい、とパークスは思った。パークスの頭には、意味もなくスザクを気持ち悪がり、ライアルと諍いを起こすリリーの姿が浮かんでいる。ライアルはスザクが苦手な人間でも、リリーに対しては怒るが、ジェンに対しては怒らないなと思ったが、パークスは深くは考えなかった。
「それは珍しいなぁ。何故だ?」
そう尋ねると、ジェンは困ったように笑った。
「両親が死んだときに、火の向こうに爬虫類のような目が見えたような気がしたんです。僕の気のせいかもしれませんけどね」
普通なら、ここで重苦しい雰囲気になるのだろうが、パークスは妖界人である。妖界人にとっては、親が死ぬなどということは珍しくもない。
「蛇系統の魔物だったんだろうな。魔界に魔物はいないが、稀に妖界の魔物が入ってしまうことがあるだろう」
パークスは、あっさりとそう言った。
「それを理由に、天界が魔界に軍を駐留させるとか何とか言っていますよね」
四界大戦の全ては、魔界に天界が軍を駐留させることで始まる。妖界としては、魔界は相互不干渉地域であり、天界としては保護地域なのである。二つの世界の違いは大きいが、魔界としてはどちらも似たようなものだった。理由はともあれ、魔界を焼け野原にする二つの世界に違いはない。
魔界はいつも火種とされ、いつも戦場となる。普通、魔界人は天界と妖界の両方を恨んでいるのだが、ジェンには全くその気がない。それは、ライアルとも同じことである。
「しかし、ライアルもお前も妖界や天界を恨んでいるようなことは言わないな。お前はキナの世話になっていたから分かるが、ライアルはそうでもないだろう」
ライアルとキナが出会ったのはつい最近であるということは周知の事実である。
「ライアルは妖界人に育てられているからですよ」
ジェンの言葉に、パークスは素っ頓狂な声を上げた。当然である。妖界人で、小さな子どもを育てることのできるような者はほとんどいない。
「妖狼王レンの名を聞いたことがありますか?」
そんなパークスの反応を楽しむかのように微笑みながら、ジェンはそう尋ねた。
「ああ、知らないはずがないだろう。十数年前、妖狼王に君臨していたからな。そいつなら納得できる。子どもを育てるだけの知性はあっただろう。ところで、知っているということは、会ったことがあるのか?」
「少しだけですが、話したことがあります。怖い顔でしたよ。妖狼って魔界の龍族みたいに、人間の姿になれるのですね」
優しい人だったのかもしれませんけどね、とジェンは微笑む。レンの記憶は、思い出したくない苦い思いで締め括られていたが、それを悟られないように笑う。
「妖界王が召喚する部下の一人のユギリス閣下も、グリフィンだが普段は人間だぞ」
妖界王は妖界王太子と同じように召喚が可能だ。被召喚者であるユギリス=ハーヴェイ妖界元帥と言われれば、知らないはずがない。
「ユギリス閣下は行方不明ですよね」
通りで強いはずですね、とでも言うように微笑みながら、ジェンは確認した。
「昔は妖界王と妖界王騎士シンスと妖界元帥ユギリス三人で、永遠のトライアングルって呼ばれていたらしいが、一体どこに行ってしまったんだか」
妖界王家を作り上げた三人の名前は、誰でも知っている。
「でも、生きてそうですよね」
元帥が死んだのならば、噂にならないはずがない。
「絶対生きているだろ。強いから」
妖界王が客として迎えた元帥である。その強さは計り知れない。妖界王自身よりも強いと言う噂もある。
「話を戻すが、何故、妖狼王が出てくる?」
パークスは、自身の世界の者が出てきたことが気になるようだった。しかし、ジェンも分からないので、首を横に振る。
「分からないんですよ。ライアルのご両親と僕の両親は仲が良いですから、僕の両親が引き取って育てても良いのに……」
ジェンは、自分の両親がライアルの両親と仲が良かったことを知っていた。姉であるキナを預かり、魔法の指導をしていたぐらいだ。相当仲が良かったに違いない。しかし、ジェンの両親がライアルを連れて帰ることはなかった。しかし、双方の両親亡き後、その真意を知ることはできない。
「あと、何故、ライアルが生きているかということだな」
偶々ライアルが生き残ったとしても、彼を妖狼王に育てさせる人物が必要だ。妖狼王にそれを命じる権力と実力を伴う人物。そうなると、自ずとその人物は限られてくる。
「アンが一枚噛んでいると思うか?」
異様なほどにライアルに執着する妖界王太子。アンのライアルに対する執着は、ジェンやパークスにも容易に察することが出来た。本人にとって、隠すつもりもない事実なのだ。
しかし、ライアルは気付いていない。自分を侮辱したキナにアンが食ってかかることがどれだけ特別なことなのかを分かっていない。
「おそらく、そうでしょうね」
しかし、理由は分からない。おそらくライアル自身も、自分とアンの関係を理解していないだろう、と二人は思った。
「無様な姿ね、サク・セイハイ」
炎の中でも決して見劣りしない鮮やかな紅色の髪が、サクの視界に入った。それと同時に、酷く冷めた声が響く。
サクはくすりと笑った。もう何十年も会っていない。さらに、彼女とは、酷い別れ方をしているのだ。しかし、サクは、遠慮なしに言った。
「ライアルに、一度だけチャンスをあげてくれないかな」
そう言って、既に力が入らないせいで、足の上に横たえただけのライアルに目をやる。
「ふふっ、私に育てろって言うの? 良い度胸ね」
「駄目なのかい?」
サクが、もう力が入らないせいで、弱弱しくなった笑みを浮かべ、そう尋ねると、アンは肩を竦めて見せた。
「あなたと夜の君主の子。大変そうじゃない」
「じゃあ、適当な人に預けてよ」
間髪いれずに、サクは言う。この時、彼に残された時間はごく僅かだった。
荒れ果てた大地に大きな狼が倒れていた。妖界に住む一民族である妖狼の男だ。
「妖狼王レン……いえ、元妖狼王って言うべきね。仲間を信用して、仲間に見捨てられ、王の座を追われたんだから」
強い風吹く荒野に紅い髪が靡いていた。それは光というよりも炎のようだった。
「噂の通りの美女だな、王太子殿下」
美しいと言われ続け、美しいことが当然だと思っている王太子は、顔に笑みを張り付け、首を傾げて尋ねる。
「死ぬつもり?」
「行きたいと思っても生きることができないだろう」
弱い者は死ぬのが妖界である。王太子は、力なく横たわる妖狼王を踏みつけるかのように立ったまま、容赦なく言った。
「命を差し出しなさい。弱いあなたに拒否権はないわ」
冷たく高圧的な声だったが、とても美しい声だった。
「この妖狼レンを弱いと言った者は初めてだ。ハイラムでも、そこまでは言わなかったからな……良いだろう。朽ちるだけの命だ。差し出そう」
最年少で王となり、長きにわたり君臨した妖狼レン。彼は強く賢かった。しかし、疲れていた。だから、彼は何の抵抗もしなかった。強く美しい妖界王太子に殺されるのなら本望だと思い、彼が首を差し出すように、顔を寝かせたその時だった。
「何を思ったの? あなたが命を差し出すのはこの子よ」
妖界王太子は敗者を容赦なく嘲笑った。その腕には、いつの間にか、すやすやと眠る小さな子どもが抱かれていた。
かくして小さな子どもの命は繋がった。
小さな子どもには力があった。それは事実だ。しかし、その事実よりも、閉ざされた双眸の色が青ではないことに意味があった。そう、サク・セイハイがセイハイとは考えられないほどに、平凡な容姿をしていないのと同じことだ。
029 TOP 031
Copyright(c) 2010 UNNATURAL WORLDS all rights reserved.